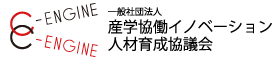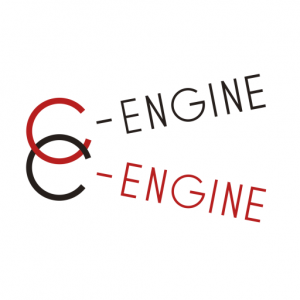人材育成の不易と流行【リトリート対談2019】
※2019年9月に発行した、当時のC-ENGINE代表理事である北野先生と、同じくC-ENGINE理事の小林様(ダイキン工業株式会社専任役員)による対談記事です。
人材育成の不易と流行:
古い硬直化した概念を見直し、新しい柔軟な発想を育む

教育システムが硬直化すると、様々な刺激を受けて成長する機会が失われる。知的好奇心を常に持ち、自分とは違う人との交流から得られる刺激にきちんと反応しつつ、さらに「社会のために役に立つ」という発想をすることは非常に大事である。これは不確実性の高い社会においても必要な、普遍的態度ではないだろうか。博士人材に対する期待というテーマで、北野先生、小林様(以下敬称略)に対談をいただいた。
”優秀な人材”という概念は硬直化していないか
ー“優秀な学生”という言い方をよくするが、非常に狭い意味で使っていたのではという反省がある。“優秀”という言葉からどんなことを想起されるか。
北野 優秀という意味をどうとるか、難しい問題だ。日本が目指してきたのは、ごく一部の人が優秀であればいいというものではなく、できるだけ多くの人がしっかり教育を受けて、共同で社会をきちんと動かすことを目指してきたはずだ。イノベーション、Society5.0というとき、ごく一部の人が優秀であればいいか、というとそんなことは決してない。
小林 若い頃、”優秀な人材”という表現を使ったら、先輩社員から、”優秀”ってどういうことかと反発された経験がある。企業では、機能別の役割分担があり、求められるスキルが違う。研究に焦点を当てると、求められているのはイノベーションを起こせる人材だ。その場合、深いところに根差した価値観、好奇心、多様性、その中でも自分の経験から一番大事なのは、ある刺激、例えば自分と違う人との交流で得られる刺激に対して、きちんと反応できるかだ。刺激がないと人間は成長できないし、新たな発想もできない。
北野 教育システムは長い時間をかけて整備されてきた。その路線に乗ってしまうと、個別の事柄に興味を持たなくてもいいし、持つと逆に評価が下がるという面がある。できるだけ引かれた路線に忠実に、あるいは先読みしてそこに行くには今、何をしたら得になるか、そういう価値判断が前面に押し出される。本人も親も先生もそう考える。初等、中等、高等教育、大学教育、就職活動において、すべてそういう感じだ。就職、入試のシステムがあって、それに適応することが大事で、それ以外は全部切り捨てるみたいなところがある。昔はゆとりがあって、趣味やサークルで何かをする、バイトでも多少クリエイティビティが必要なものもあった。そういう機会を利用して刺激を取りに行っていた。今回のインターンシップもそういう位置づけで、大学以外のところに行くことが刺激になって、そこの課題を見ることで、考えてみようか、一肌脱いでみようか、という気持ちになる。
小林 企業のマネージメントから言うと、2・6・2の法則があって、上位の2割は放っておいてもしっかり仕事をする。真ん中の6があって、どうやっても動かない2がその下にいる。マネージメントは、真ん中の6をやる気にさせて、有能にすることだ。教育も同じようなことかもしれない。放っておいても勉強する2ではなく、真ん中の6をどう底上げするか、それが教育なのかと。上位の2は、優秀な師匠、先生といった刺激を受ける人と出会って、その考えを吸収することができるのではないか。これまでの経験から、学校でも企業でも、この人から影響を受けた、という人はいる。自分にない考え方を植え付けてくれる、言動の中から学べる人たちだ。
北野 その層は、自分だけが良ければというのではなく、社会性、全体性を考えて動けるかがポイントなわけだ。個人のエゴ、組織のエゴに走ってしまったら、社会は変な方向に動く。上の層の人たちの行動や考え方はとても大事だ。
博士人材の評価も変化している
ー社会的課題は大学にとってある種の刺激だ。これに対応できる人材を育成しようという教育プログラムが、大学院改革の一環として提起されたが、その成果を企業はどう評価しているか。
小林 博士課程でも、リーディングプログラム、卓越プログラムでも、インターンシップを含め、いろいろな経験をさせるプログラムが出てきて、企業側から見ると、博士課程の学生の見方がだいぶ変わってきた。
北野 大変ありがたいお話だ。
小林 ダイキンの中で、日本で働く人が1万人弱、9500人くらいいる中で、博士課程出身者は84人。その中で30数人が化学系、機械・電子系は50人弱だ。全体の事業、人員の規模でいうと、9対1で、化学系は小さく、1割くらいしかいないのに、博士が多い。専門性が高い部署は従来から博士課程の学生を採用していたが、機電系はそんなに要らなかった。しかし、最近はリーディングプログラムを履修した博士課程修了者の評価が高い。従来の博士人材の評価が変わってきたように思う。C-ENGINEのインターンシップにおいても、博士課程の学生は、やっぱり違うなと思うところがある。今後、博士人材に注目していきたい。
北野 C-ENGINEのインターンシップもリーディングプログラムも卓越大学院も、まさにそこを目指しているが、効果が中々見えてこなく、やっているほうは不安もある。今のようなお話を、いろいろな企業からも言っていただけると、やりがいがある。
ー具体的に、博士人材はどんなところが優れていると思うか。
小林 20年近く、定期採用の面接をやってきて、企業としては研究部門に採用する場合、博士課程、修士課程の学生が唯一の即戦力だと私はみている。博士課程の学生は6年間研究をやってきているので、一連の研究活動は全部経験している。分野は違ったとしても研究のプロとして、プロセスは熟知している。
北野 博士までいくと、学術論文を書いて、レフリーから返ってきたものを書き直すというやりとりを経験している。修士だと内容は作れるが、論文投稿が間に合わなくて社会に問うことができていないケースがある。博士まで行くことによって、本当のトレーニングを受けている。
小林 挫折をも含めて、自分の考えに基づいて進めようとして、紆余曲折を経て何かを得ている。
北野 そこで何かを掴んだ経験はとても大きい。博士の学生でもオーバードクターを何年もやることもあるが、結果的にそれなりに皆頑張っている。化学系は大学でも博士の割合が多い一方、機械系は少ない。化学系は博士までいって、ある程度専門性を深めないと使えない。日本の上位の企業の力が弱まっている中で素材メーカーは世界的に力があり、それなりのポジションを維持しているのは、そういうところに理由があるのかもしれない。博士人材を採用していない分野は、競争力が弱く、戦っていけないのだと思う。幸い、素材や化学系のメーカーは競争力があるところが多い。
小林 去年、C-ENGINEのインターンシップに参加した阪大の女性が、今、当社のテクノロジーイノベーションセンターで働いている。今、実習中で、先日、最終報告会があって参加した。さすがだなと思ったのは、専門ではない技術分野で、自分の専門のデザイン工学の手法でバリューデザインの手法を植え付けたことだ。教育される場合が多いが、博士人材が先輩の知らなかった手法を教えたというインパクトはとても大きい。こういうことが博士人材には期待できる。博士人材は、専門で勝負する人がいてもいいし、広さで勝負する人がいてもいい。我々、企業の人間が感じるのは、大学の専門性の構成比と企業が求める人材のそれがマッチしていないということだ。バイオ、材料創成、宇宙を専攻する学生が来るが、就職のチャンスは少ない。我々がほしい、機械系の学生は少ししか来ない。そうであるなら、専門性で採用するのではなく、研究プロセスのプロとして採用するという方法もある。とりわけ、博士の学生として尖り過ぎると、逆に採用しにくくなる。
知的好奇心を維持・増強し、キャリアパスを明確にすることが重要
ー博士課程への進学者が減少し続けている。様々な要因が考えられるが、知的好奇心という切り口で考えてみたい。
小林 知的好奇心は誰でも生まれつき持っているのではないか。定期採用の面接をしていて、魅力的な学生がいる。ある女性は、特許が専門の修士だったが、学部は機械工学、修士は他の大学の大学院に進んだ。その場で採用を決めるので是非、入社してほしいと頼んだ唯一の学生だ。自分がキャリアパスとしてやるべきことを学生のときからイメージしている。大学入学がゴールだと思っている人は多い。こういう学生は稀有だ。
ー稀有な理由は?
北野 それは教育システムの弊害とも言える。大学に入ること、有名企業に入ることを親が先回りして考えてしまっている。知らず知らずのうちにいろいろな介入がある。小学校から大学まで親が決めるケースが多くある。その環境の中で自分を失わず頑張れるか、ということかもしれない。
知識やスキル以外で大事なこと
ーインターンシップでは、スキルや知識を身につけてほしい、と学生さんに言っているが、それ以外にも、価値観に触れるといったことが大事であると思うが。
小林 価値観という言葉には当てはまらないが、知識やスキル以外で大事だと思うことは、イノベーション。人が考えつかないことを考えられるオリジナリティ、これがないとイノベーションは起こらない。オリジナリティを追求する心。もう一つは、突破力。ものを実現しようと思うと、必ず障害が出てくる。最後に責任感。自分がやり遂げる、といった覚悟だ。会社の中での経験からこの3つが重要だと思う。人間力と言い換えることもできるかもしれない。
北野 研究には、大きく3つのモードがある。一つは好奇心で導かれる学問のための学問、ピュアなサイエンス。二つ目は、経済的に役に立つもの。もう一つは、社会的課題の解決を目ざすもの。学問は一つ目のモードから始まり、時代とともに二つ目、三つ目へと展開してきた。大学でも二つ目が主流になりつつあるが、さらに三つ目も必要で、大学の社会貢献が求められている。このバランスを一人の人間の中でとるのか、社会としてとるのか、リーディング大学院や卓越大学院では一つ目のモードだけでなく、第二、第三のモードにも手を伸ばしてほしいということだ。アカデミアとインダストリーのマッチングもそういうところで考えていかなければならない。
”社会の役に立つためには”という発想が必要
ー大学も企業も、個人と社会のWell-Beingを目指している、という点では共通だ。手段と役割の違いを相互に理解した上で、もっと歩み寄って人材育成に取り組むことができると期待している。
小林 経営工学的に言うと、顧客満足度(CS)を高めるためには従業員満足度(ES)を上げなければならない。やる人たちが、やる気をもってやらないと企業業績は上がらない。研究所長時代、テーマを選ぶときに、会社のためになること8割、やる人たちのモチベーションが上がること2割くらいのウエイトで決めていた。最終的に企業業績を上げるためにも、やっている人たちがやりがいをもってやれることが大事なように思う。
北野 世の中では、会社は株主のためにあると言われているが、その弊害も出ている。
小林 会社では、ステークホルダーという言い方をしている。従業員、株主、地域社会、顧客、全体がハッピーになる、と。企業が永続的に活動を続けるためには、利潤を上げることが大前提だ。その過程において、従業員のモチベーションを上げる、地域社会と仲良くやる、ということはあっても、それが目的ではない。利益を追求するためには、社会の役に立たなければならず、それを常に考える必要がある。最初から入ってきた人と途中から入ってきた人たちでは、その辺の感覚が違う。同じ会社でやってきた人は狭いところでしか考えていないが、例えば、途中入社の、ベンチャー企業の社長経験のある30代前半の若い人は、もっと幅広い視点で社会の役に立つためにはという発想ができる。自分の技術を持っていないために逆に縛られずに発想できるように思う。
北野 総じて大企業は、利潤追求や市場拡大を優先し、社会のためにという部分を忘れて、自己保存のために動いているところがある。特に大きな会社がそうやって動くと、世の中がおかしくなるケースがたくさんある。今のお話にあるような、新しい意識のある人が入ってくることで、あるいは、博士人材が組織の中に入ることで、全体を俯瞰して判断できるようになることが大事ではないか。大企業でも、学部卒で元気だけあれば十分、と豪語するところがかなりある。既存の価値観だけで硬直化した活動しかできなくなる恐れがある。どこかで崩していかなければならないのではないか。