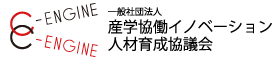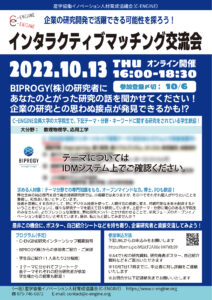人材育成をめぐる回顧と展望【リトリート対談2022】
研究者自身が社会とのつながりを意識し「社会のために役に立つ」という発想をすることは非常に大事であるというポリシーのもと、人材育成をめぐる回顧と展望というテーマで、当協議会の平島理事長と小林理事にご対談いただきました。
-刺激とやる気、啐啄同時-

―学生はどのように自身の研究に社会とのつながりを意識していくか。ご自身の経験ではいかがでしたか。
平島 はっきり言って、理学の世界では直接的な社会貢献って難しいんですよ。私の分野は地球科学、専門は岩石学ですので、その場合一番関係がありそうなのは、地震予知です。昔の沈み込み帯、プレートが地下20km、30km、100kmと潜りこんでいくうちにいろいろな鉱物の変化が起こっていきます。石に入っている鉱物の種類や組成で、この岩石が潜り込んだ深さや温度が分かる、これが最初の専門でした。それに取りついたきっかけは、修士のときについた先生に、「この教科書に書いてあることは間違っていると思うから自分で確かめろ」というところから始まりました。だから社会貢献でも何でもなくて、学問の世界の説が合っているか間違っているか、そこから入りました。
―博士人材の真価はどのような教育あるいは経験から生まれるとお考えですか。
平島 1985年に助手になってから教授職やめた2020年まで、ちょうど35年間教育に携わりました。その間の卒業生の進路を調べてみると、2割の学生は大学や国研の研究者になっています。教育において力点を置いたのは、どの分野に行っても役立つように、まず自分で問題を設定して、その問題を解決するための作戦と実験計画を立て、時間内にそれをまとめて必ず発表する、ということでした。修士論文では卒論をさらにレベルアップさせ、大学院、博士課程に進む場合は英語で書くように指導していました。卒論ゼミから、とにかくどういう問題をやるか、課題は何か、その課題を解決するためにどういう作戦を立てるか、研究計画を立てて、それを遂行する。自前の機器で実験ができない場合は無料でできるところを探して、実験させてもらう。科研費があれば外注をする。実験をさせてそれを最終的に発表する、つまり論文を書くことを徹底的に教えます。結局、研究の世界で生き残ろうと思ったら、昔の人たちが言っていた”Publish or Perish”、つまり、「書くか、死ぬか」、ですよ。それをゼミで徹底しました。
もともと私は京大理学部に入学しましたが、「お前は何をやりたいんだ」と言われて、「これをやりたい」と言ったら、先輩方が他の大学に行けと言ってくれましたので、修士課程は金沢大学に行きました。その時の指導教員が、めちゃくちゃ厳しい先生で、そこのゼミでは大学院生が下手な発表しようもんなら、突っ込みに突っ込まれて泣き出す人もでるような。これはえらいところに来てしまったと思いました。そこでは自分で発表する限り、参考論文を徹底的に読んでよく理解して、自分の言葉で喋る、そういうスタイルを徹底しました。修士修了時に指導教員が京大に移られたので、私も博士課程は京大に戻り、その後幸運にも助手に採用されましたので、指導教員から受け継いだこの伝統は私が定年するまでずっと続きました。
―企業に入ると、学生の時との意識の違いは何だと思われますか。
小林 僕は京大の原子力工学を卒業して、院には進まずダイキン工業に就職しました。大学院は理学部から来る人も結構いましたが、先生が言われたように、博士課程修了者は研究のやり方自体を会得している、僕はそう思っています。企業の研究部門で博士課程の人間は即戦力になる、修士であれば2割は即戦力、そんな印象をもっています。学生と企業人の違いって何だろうなって考えたときに、やっぱりお客さまがいるっていうこと、突き詰めるとそのことなのかなと。顧客に向けて、顧客価値を提供して、対価をいただくというのが基本的に企業なので。それに対して役割分担をするのが基本的な違いだと思います。技術系では、QCD(クオリティ・コスト・デリバリー)、この3つの意識が出てくるのが技術系企業人なのかなっていうのが僕の考えです。商品開発の人たちは、開発したいものを図面に落として、商品として生産して世の中に出すということをしています。僕はやったことないながら、商品開発で一番大事なのはコストかなと思ったら、実はデリバリー(納期)なんです。僕は研究出身ですが、研究は一言で言うとクオリティのみ。いい技術が出なければゼロかイチかなんです、研究は。そういう意味ではクオリティ。役割によって違うんですけども、技術系としてまとめるとQCDかなと思っています。新入社員の中から100人選んでAI人材を育てるダイキン情報技術大学の一期生で、とても優秀な社員がいるんですけど、彼に学生のときと企業に入ってからの違いはなんだと聞いたら、彼もQCDだと。やっぱり若い人も同じ感覚なのかなと思った記憶があります。
―企業あるいは大学の研究者として力を伸ばすことができるのはいつ頃とお考えですか。
小林 企業に入ったのが40年前なのでビビットな感覚は残っていないんですが、振り返ると、僕は研究に入って、小規模ながら自分で技術開発をして特許を取り、それを商品開発部隊に移管し、それが商品として出ていった数は周りの人より多かったのではないかと思います。商品を開発し、世の中に出す過程で、他の部門と協力、役割分担をしながらやっていくことでだんだんわかってきたんじゃないかなっていう気がします。入社して4〜5年くらいですかね。
平島 私の研究室でも同じことを感じます。学卒で企業に入られて4〜5年であればちょうどドクターくらいでしょう?
小林 そうですね。
平島 私の研究室でもマスターまでは自分の専門領域をまずはやる。ドクターになったら、隣の講座にも関心を持つようになって、他のいろいろな分野と関わり、交わるんですね。能力のある学生はそこでぐんと伸びていく。そういう学生が京大にはいますね。ただそれにはドクターまで行ってくれなきゃいけない。今の課題は、かなり優秀な学生が、マスターを修了後、ぐんと伸びる前に企業に就職してしまうことです。
―仕事に対する意識の変化を感じることはありますか。
小林 僕は約20年間、定期採用で1000人程の学生と面談したと思うんですけど、ダイキンはかなり環境負荷の大きな製品を作ってるので、地球環境問題って結構ビビットにやってるんです。それで言うと、10年前の学生は、なぜダイキンを志望したんですかと聞いたら、環境問題に取り組みたいからと。僕から見ると建前で言っていたように思います。最近は本気で言う学生がほとんどですね。どうも聞いていると本気で言っているなと。そういう所はだいぶ変わってきた感じがしますね。入社式もダイキンは結構独特ですが、500人くらいの新入社員を、ひとりずつ名前を呼んで、立たせて顔をみんなに見せることになっています。コロナの影響があって、今年の4月は映像で顔と抱負をひとりずつ流していくというやり方でしたが、僕がちょっとびっくりしたのは、仕事と趣味の両方頑張りますっていう人が新入社員の半分くらいいたんですよ。200人くらいかな。中途採用の方にはいなかったんですが。
―採用では、どのような工夫をされていますか。
小林 人事制度については今の会長も社長も人事出身なので結構独自の施策をとることが多くて、「従業員と会社というのは選び選ばれる関係で、双方が選ぶという関係」という考え方が昔からあったんですよ。採用選考時にも「面接」ではなく、「面談」と言って、こちらから質問をしますけれども、学生からの質問も受け付けて、お互いに知り合う場という捉え方をしています。こちらも選ぶけどあなたも選んでください、もし入ったらロイヤルティ、愛社精神を持ってくださいと。そういう風に、人を基軸とした経営をこれまで我々はコアに据えてやってきたんです。ただし、今の世の中、例えばAI人材が企業で取り合いになり、ダイバーシティがいろいろなところで叫ばれ出して、愛社精神を求めるだけではなかなか人材が集まらない。多様な雇用形態で多様な人材を集めるようにシフトしようとしているのが現状だと私は理解しています。
―ジョブ型採用については?
小林 おそらくその職種に就職するのか、企業・組織に就職するのかということではないでしょうか。もともと欧米なんかでは職種に就職、日本では会社に就職していた。今では日本でも職種によっては職種に就職するっていう感覚をもつ人が増えてきたのかなっていう印象ですね。専門的スキルを持つ人は渡り歩けるので、そういう人が増えてきたような気はします。
―採用でも、ジョブ型採用が増えてきていて、欧米型のジョブ型採用に日本企業も移行すべきという議論がある一方で、現実問題として従来の日本型のやり方をやめて、新しい仕組みを一から作り直すとなると、企業にとってもそこまでの方針転換はなかなか難しいように思いますが。
小林 ダイキンは、ハイブリッド型でやってます。定期採用は400人くらい、中途採用は100人くらいいるんですが、ジョブ型採用と一般的な採用を併用している。特に中途採用は職種を限定して採用するし、その中途採用比率が上がっていることを含めると、ハイブリッドではあるけれどもこれからジョブ型採用の比率がだんだん変化していく気がします。
―研修や育成の特徴は何ですか。
小林 新入社員の合宿訓練もその一環かもしれないし、いろいろなところで独自の施策があるので。ちょっと変わった会社ということは面談のときも入社のときも言いますからね。そういう独自性を気に入ってもらいたい。例えば、一部上場企業で管理職の試験がないのは多分うちだけだと思うんですよ。他の会社はだいたい課長になると試験があるところが多いんですが、うちはそういうのもなく、一人ひとりを見ます。従業員教育についても、システムとしての教育制度というのはあまりないですが、部門長が思いついた教育を始めたりする。例えば私が研究所長をやったときに、研究者の育成制度を作ったんですね。キャリアデベロップメントプログラムという。研究者はそれぞれ少なくともその分野ではダイキンで一番、あるいは日本で一番、できれば世界で一番というものを持っている。そういう研究者であれば、他の誰もその人の育成計画は作れない。だから自分で自分の育成計画を作ろうというもので、一泊二日で刺激を与えて、5年後の自分の技術屋としてのイメージを持って、そうなるための育成計画を作らせるんです。講演を聞くとか、本を買うとか、育成のプログラムに参加するとか、それに必要な費用は会社から出すからと。そういうプログラムを作りましたけど、次の研究所長になるとまた考えは違うから、別のものに変わるというような。会社全体の仕組みというよりは、後輩を育てる文化はありながら、人それぞれ違うやり方を取り入れています。
平島 会社に入ったときの新人研修はどれくらいやられるんですか?
小林 2ヶ月くらいですかね。
平島 専門メーカーだからですかね。僕の教えた学生の中で資源系のある会社に行った学生は、1年だったそうです。いろいろな部署を3ヶ月ごとに回らされて、1年経ってから配属先が決まる。そういう会社もあるんだと思いましたが、今は少数派なんでしょうか。
小林 我々の研修も、人事部門が預かるのは2ヶ月くらいで、それから部門に分かれて研修があるところもあるし、テクノロジーイノベーションセンターという開発部隊と研究部隊が一緒になったところの開発部隊では1年くらい研修させたりするようです。開発か研究か等でも少しその期間は違うようです。
平島 ダイキンさんの今のスタイルでの離職率ってどうなんですか。
小林 以前はすごく少なかったんです。たぶん1%前後くらいだったと思うんですけど。最近は増えてます。若い人は3年で10%くらい辞める感じ。定年退職も含めて言うと、離職率の平均は4.3%くらいかな。
平島 でも低いですね。
小林 平均よりだいぶ低いとは思います。さっき言ったように愛社精神を求めてますから。
平島 それが成功の秘訣かもしれませんよ。人材がひとつのところに腰を落ち着けて仕事ができる。
―今後、社会から期待される博士人材像について、お考えを聞かせてください。
小林 先ほどのジョブ型みたいなものを含めて、個人的な意見かもしれないですけど、最後は企業、大学もそうなのかもしれないですけど、最終的にはマネジメントできる人間がほしいわけです。それでいうと、特定のスキルを持っているジョブ型の人間は、そのマネージャーの対象にあまりなりにくいので、組織としては期間限定の雇用形態をとりがちになると思います。一方で、先ほども先生も言われたと思うんですけど、例えば博士課程の人間って、何のために採るんだって研究部門の幹部と議論したことがあって。僕はマネジメント能力だと言い、別のある人は専門性だと言う。あくまでも僕の印象ですが、最近博士人材のマネジメント能力が上がってきているように思っていて、それを目的に採る企業も増えてきているのではないかと思うんです。というのは、空調の勉強をしている日本の大学生はほとんどいないんですね。空調の専門的知識を教える大学は日本にはほとんどないので。そういう意味では他社も同様に、専門性じゃなくて、マネジメント能力を求めて博士人材を採用しているのではないかと。最近の博士人材は特に、そのマネジメント能力が評価されて、価値を認められてきているように思います。
平島 博士のマネジメント能力が上がってきたひとつのきっかけは、日本学術振興会の奨学金DC1、DC2によるところが大きいように思います。修士からドクターに上がる前に、DC1に申請する。それがもらえたらドクターに進むという、それくらいの奨学金なんです。その奨学金を受けるために、専門外の人が読んでわかる申請書を書くトレーニングをM2から始めます。それ以降の世代は、博士課程に行ってもある限られた時間内である程度の成果を出さなければいけなくなっていて、そこでマネジメント能力が向上していると思います。これは大きい。私の時代にはなかったことです。
―大学院生へのメッセージをお願いします。
小林 若い世代が社会で求められる人材となるための大学教育としては、企業が求める人材というところからも考えていただきたい。僕が若い人に必ず言うのは、自分の存在価値というか、オリジナリティを持ってほしいということ。僕が研究出身だからっていうのもあるんですけども。どんな職種に行ったって、わかりやすい言葉で言うと「休んだら困られる人間になれ」って言います。そのためには自分なりのオリジナリティであったり、自分の得意な領域であったり、そういったものを見つけてほしいんですよね。とりわけ研究部門で言うと、先ほどの先生の話のように、自分のテーマは自分で作るということ。少なくとも僕は入った2年目以降は自分のテーマは自分で作ってきた自負がありますが、今の若い人はそこが弱いように感じています。「私のやりたいことはこれだ!」と、決して独善的にならず、会社の状況を理解した上で、自分のやりたいことが会社の役に立つという両側面を考えて提案できるような、そういう人になってほしい。それに若いうちから挑戦してほしい。やはり柔軟な、イノベーティブな発想っていうのは若いうちでないと出ないと思っています。だから普段から若い社員には、「君たち、そんなもう時間ないぞ。研究者の定年はすぐやって来るんだから、最初から遠慮せず自分のやりたいことを提案していけ。」と言っています。大学でも、そういう人間が育つような教育をしていただけたらありがたいなと思いますね。
平島 近年、東大・京大の優位性は、だんだん減ってきていると思います。学生の質が、がらっと変わってきているんです。それは、好きなものだけ勉強してきて、他を捨てるという受験勉強の仕方にあると思います。東大生とか京大生で就職できない学生のほとんどは、コミュニケーション能力が不足しているだけで、地頭は良い。そういう学生は、特異な能力が活かせるところを探し、うまくアピールしなければならない。
小林 確かに、地頭が良くても、それでマイナスになってしまう人はいますね。
平島 東大や京大にストレートで入ってくる学生の中にも、M1の後半になってやっと、自分のコミュニケーション能力が不足していることに気づく学生がいる。そこで修正しないといけません。能力の高さだけでは生きていけない時代になっているんですよね。
小林 ダイキン情報技術大学(新入社員を100人集めて2年間、勉強だけさせるところ)でPTA会長みたいなことをやっていますが、彼らと向き合うときに思うのが、失敗を恐れる若者が多いこと。イノベーションを起こすのであれば120点を狙っていくべきで、最初は10点でもいいはずなのに、80点狙いで無難なところに置きにくる。挑戦もせず、傷つきたくない、人から後ろ指さされたくないっていう思いが強く感じられることがありますね。
平島 京大の学生には、天性の、すごく高いパフォーマンスを持つ人材がいます。そういう特異な能力を持った学生に、コミュニケーション能力をなんとか改善させてあげたいと周りから働きかけても、本人に気づいてもらわなければどうにもならない難しさがあるんですよね。
小林 そういう学生には、うちでの研究インターンシップにぜひチャレンジして欲しいです。やっぱり刺激が一番だと思うんです。何かの刺激を受けないと変わらないし、成長しないと思います。欧米のことわざで「馬を水飲み場に連れて行くことはできるけれども、馬がその気になれなければ飲ませることはできない」というのがあります。周りの人間ができることは、刺激を与えることだけです。気づくかどうかわからなくても、何かの刺激を与えられる場を設定するしかない。研究インターンシップは、社会に出ていくには磨くべきスキルがある、特異能力をもった博士人材と、新しいことへの挑戦心を必要とする若い社員が相互に刺激しあえる機会としても実は最適なのかもしれませんね。
以 上